電気を語る上でもっとも大切な公式が、オームの法則と合成抵抗です。
電気の世界における「1丁目1番地」。言うなれば、算数の足し算・引き算にあたる基本です。
第二種電気工事士の筆記試験では、必ずといっていいほどこの2つの考え方が出題されます。
公式を覚えるだけでなく、「電気の流れをどうイメージするか」が得点のカギとなります。
この記事では、初心者にもわかりやすいように、
公式の意味・使い方・よく出るパターンを図解と具体例を交えて解説していきます。
この記事を書いている人
- 電気工学を大学で4年間専攻
- 第一種電気工事士、1級電気工事施工管理技士、高校教諭免許(電気)を取得
- 大手電気工事会社で10年間、現場監督・施工管理を経験
- 現在は製造工場で電気保全を担当
- 資格と現場の両方から「実務に活かせる電気」をわかりやすく発信中!
オームの法則とは?公式と使い方を解説
オームの法則は、電気の基本中の基本である以下の公式です。
V(電圧)= I(電流) × R(抵抗)
この関係を覚えることで、次の3つの値のどれか2つがわかれば、残り1つを計算することができます。
| 記号 | 意味 | 単位 |
|---|---|---|
| V | 電圧 | ボルト(V) |
| I | 電流 | 電流(A) |
| R | 抵抗 | オーム(Ω) |
このオームの法則は電気理論では必ず使う公式になるので、覚えましょう。
覚えやすい図:「VIRの丸図」
オームの法則を覚えるときによく使われるのが「VIRの丸図」です

この図を使うと簡単にオームの法則を簡単に覚えることができます。
試験での出題パターン
オームの法則は次のように使います。
・電圧が100V、抵抗が10Ωのとき、電流は何Aか?
この場合、電流Iを求めたいので、
I=V÷Rより
I=100/10=10(A)
電流は10Aとなります。
このようににオームの法則は使います。
はじめは難しいかもしれませんが、オームの法則を覚えれば解ける問題がぐっと増えます。
また、オームの法則は「電気の基本のき」であり、電気を理解する上で重要な公式になります。
合成抵抗とは?直列と並列の違い
合成抵抗とは、複数の抵抗器がつながった回路において、それらを1つの抵抗としてまとめたときの値を「合成抵抗」といいます。
この合成抵抗を求めることで、オームの法則(V = IR)を使った計算がしやすくなります。
直列回路の合成抵抗:足し算でOK

直列回路では、各抵抗を単純に足し算します。
例題:上記の図のRa,Rbの抵抗がそれぞれ10Ωである。この時の合成抵抗Rabは?
回答:直列回路の合成抵抗は足し算であるので
Rab=Ra+Rb=10+10=20(Ω)となる
直列回路の合成抵抗は単純な足し算であるので、試験に出てきたらサービス問題と思って必ず得点に繋げましょう。
並列回路は「和分の積」で覚えよう(証明つき)

並列回路では、「和分の積」で合成抵抗を求めることができます。
これはもともと、逆数の公式から導かれるものです。
●証明してみよう
並列回路の基本公式は:
1 / Rab = 1 / Ra + 1 / Rb
通分すると
1 / Rab = Rb / (Ra × Rb) + Ra / (Ra × Rb)
= (Ra + Rb) / (Ra × Rb)
ここで両辺を逆数にすると:
Rab = (Ra × Rb) / (Ra + Rb)
実際の試験では、第二種電気工事士の試験では「和分の積」だけ覚えていればOKです!
確認問題にチャレンジしよう

解説:まず上記の図を整理しましょう。
- 並列回路である
- 抵抗は20Ωと30Ω
- 電源電圧60V
並列回路なので、公式「和分の積」を使います。
R合成 = (20 × 30) ÷ (20 + 30)
= 600 ÷ 50
= 12Ω
次にオームの法則より
I = V ÷ R
=60 ÷ 12
= 5A
答え:回路全体に流れる電流は5Aとなる
解法ポイント
- 並列回路の合成抵抗は「和分の積」でサクッと求められる
- オームの法則(I = V ÷ R)で全体の電流を求めればOK!
まとめ
- オームの法則(V = IR)は、電気理論の基本中の基本。
計算式は「丸図」で覚えると便利です。 - 合成抵抗には「直列は足し算」「並列は分数(または「和分の積」)」の違いがあります。
- 並列回路では、「和分の積」で簡単に計算できます。
- 電源電圧と合成抵抗がわかれば、オームの法則で全体の電流が求められる
- 実際の問題では、直列・並列の見極めが最重要ポイントになります。
これから学習を進める人へ
第二種電気工事士の筆記試験では、オームの法則や合成抵抗の問題が高確率で出題されます。
ここで紹介したような計算パターンを理解して、過去問で繰り返し練習することが合格への近道です!



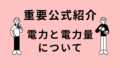
コメント